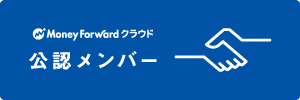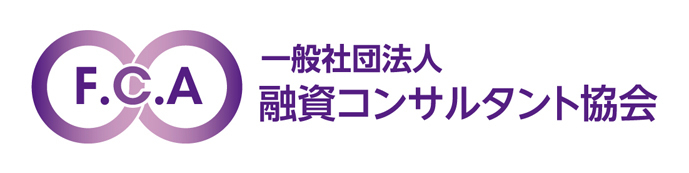お電話でのご依頼・お問い合せはこちら
資金繰り表の作成と活用

「黒字倒産」という言葉を耳にするように、決算書の損益計算書上では利益がでて黒字の数値なのに、資金繰りが切迫していて、結果ショートしてしまい倒産に至ってしまうケースがあります。
会社の倒産の理由に、現預金の資金が不足で起こることもあげられます。
売上が伸びているから資金も手許に残っているものと思い、経理からの報告に、思っていたより手許資金がない、資金が足りないと慌てて借入をお願いするといったこともあり得ることだと思います。
資金が足りているのか、先何か月まで資金が手元にあるか、設備投資するとした場合にどのくらいの投資に充てられるかなど、資金繰り表を作成して資金の流れを管理することで、経営の上での判断にも役立ちます。
《目次》
1.資金繰り表とは
2.借入時の判断による資金繰り表の活用
3.資金調達余力の考え方
4.まとめ
資金繰り表とは
資金繰り表は、事業の資金の収支の流れを表す表になります。
決算書の損益計算書は、売上や仕入れの事実にもとづいて会社の「損益」を表したものになりますが、資金繰り表は、売上の入金や仕入代金の支払い、設備投資の支払いや借入金の返済による支払いなど資金の収支の事実にもとづいて、会社の資金の残高や資金の流れを現す表になります。
売上・仕入の計上と入金・支払いのタイミングについては、日々の取引においても多くの場合にズレが生じています。
例えば、飲食店や小売店で、お客さまが売上時にクレジットカードで支払いを行えば、売上の計上の時期と売上代金の入金のタイミングはズレてきます。また同じように、仕入れ時においても当月仕入れたものを翌月末に支払う場合、仕入れの計上の時期と支払い時期のタイミングも同じようにズレが生じてきます。
このように、会社の損益を示す損益計算書と資金の収支の流れを示す資金繰り表とでは、異なる数値の結果になります。
損益計算書が黒字でも、資金繰りはマイナスであったり、反対に損益が赤字でも資金繰りはプラスになることもあり得ます。
資金繰り表を作成することで、先々の「資金の流れ」や「資金の残高」の見える化に役立ちます。
借入時の判断による資金繰り表の活用
金融機関の借入融資申し込みの際に、資金繰り表の提出を求められることがあります。
融資の際に重視される点は、資金使途と返済原資になります。
資金使途は、「設備投資」への資金の使いみちと「運転資金」への資金の使いみちと区分されます。
「設備資金」の場合は、何の設備に投資をするか事前に計画があれば購入先からの見積書からいくらの金額が必要なのかと確認がとれます。
また「運転資金」の場合は、これから先の事業の運営にどのくらいの資金が必要になるのか資金繰り表をもとに確認することができます。申込時の借入金が妥当な金額であるか数字から判断することもできます。
資金繰り表を作成して先の資金の流れをみていることで、金融機関からみても数字管理ができている会社として見られ、融資返済の説得力を持たせます。銀行融資の際の受けやすさも格段に変わります。
資金繰り表は半年間から1年程度を目安に作成され、事業の流れの変化で数値を更新して先の資金の見通しをつかんでおくことが重要になります。
資金調達余力の考え方
資金調達余力とは、金融機関からの借り入れに際して「あとどれくらい借りられるか」という追加で資金を調達する力を判断する指標になります。
この指標を把握しておくと自社にとって借入できる目安を立てることができ、資金繰りを考えて行くうえでも役に立ちます。
資金調達余力には明確な指標や計算式があるわけではなく、また金融機関ごとにも融資限度額が異なるため、「過去にどれくらいまで借りることができたか」が一つの判断基準と考えられます。
①信用保証協会付融資
信用保証協会とは、金融機関に対して債務の連帯保証を行う公的な保証機関になります。
信用保証協会にも独自の審査機関があり、決算書をもとにして信用保証協会内の審査により保証の可否が行われます。過去にどれくらいまでの保証がされたかの実績が一つの目安と考えられます。
決算内容が大きく変わらなければ過去の融資額まで、借入することが可能な場合が多いです。決算の業績が向上していれば、保証も同額ないし同額以上を期待できることも考えられます。
また、決算書を金融機関に提出した際には、金融機関は保証協会へも提出します。その際に担当者へ保証枠の確認をお願いしておくと保証協会から目安を教えてくれることもあります。
②取引金融機関のプロパー融資
信用保証協会と同じく、過去にいくらまで借入ができたかが一つの目安になります。
金融機関ごとという考え方もありますし、すべての金融機関の合計という考え方での判断もされる場合もあります。
資金調達余力についての指標や具体的な算定は難しいですが、返済実績に基づくことから、過去にいくらまで借入が実行されたか一つの目安と考えられます。
まとめ
実績が悪くなってから借入を申し込むとなると対応が遅れることが多くあります。
そのため、日々の資金の収支の流れは把握し、資金繰り表により3ヶ月、半年、1年先の収支のバランスの流れについて確認とることは、「いつ、どの時点で、いくら資金が必要なのか」が明確にもなり、事業経営におきましても資金の流れの判断に重要なことといえます。
いくら損益計算書上で利益が出ていても、資金の不足によって黒字倒産ということも考えられます。重要なことは儲けた利益がどのに消えているのか確認するためにも、損益と現預金のズレを資金繰り表からも理解していくことが大切です。
また、借入融資申し込み時にも、過去の数値結果の試算表だけではなく、これから先の事業の経営数字の説明に資金繰り表を提示して数字による根拠を説明することで、説得力を持たせることにもつながります。
資金繰り表など借入融資申し込みの資料を作成できない場合や作成のポイントを確認したい場合には、専門家のアドバイスを受けながら作成することがおすすめです。
事業資金や資金繰りに関するご相談に、融資・資金調達支援コンサルティング、キャッシュフローコーチ・コンサルティングの各サービスをご用意しております。
関連するページのご紹介
こちらのページを読んだ方には、下記のサービスページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
お問い合せ・初回のご相談はこちら

税務・財務のご相談を受け付けております。
アクセス
住所
〒110-0005
東京都台東区上野3丁目16-2 413号
最寄り駅
・JR 御徒町駅より徒歩4分
・銀座線 上野広小路駅より徒歩4分
・大江戸線 上野御徒町駅より徒歩4分
・千代田線 湯島駅より徒歩4分
・京成線 京成上野駅より徒歩9分
・JR 上野駅より徒歩12分
営業時間
9:30~18:00
定休日
土曜日・日曜日・祝日