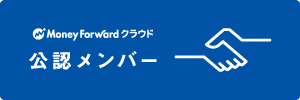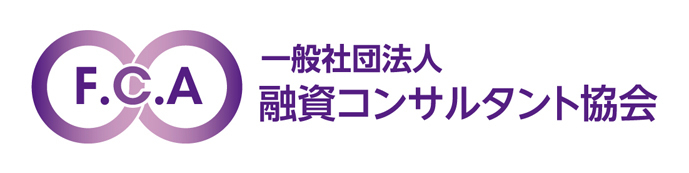お電話でのご依頼・お問い合せはこちら
電子帳簿保存法と改正のポイント

電子帳簿保存法とは、会計帳簿や会計処理の根拠となる証憑書類を紙での保存でなく、電子データとしての保存を認める法律です。テレワークの導入やデジタル化が進む中で、ペーパーレス化による効率性や生産性の向上も期待できます。
電子帳簿保存法は制度が制定されてから改正を重ねており、電子データの取扱いが簡易化されてきております。
ここでは、会計業務のペーパーレス化やキャッシュレス化における電子帳簿保存法とその改正のポイントについて説明します。
《目次》
1.電子帳簿保存法とは
2.電子データの保存方法
3.電子データの保存要件
4.電子帳簿保存法の申請方法
5.2020年改正のポイント
6.まとめ
電子帳簿保存法とは
電子帳簿保存法とは、今まで紙での保存が義務づけられていた税務関係の帳簿書類を一定の要件を満たすことで、電子データによる保存を認める法律になります。
企業や事業者が日々の事業を行うなかで、請求書や納品書、領収書などの取引に関する書類や取引内容を記載した仕訳帳や総勘定元帳など多くの国税関係帳簿書類が発生します。
これらの帳簿書類は原則、紙媒体で保存することと義務付けされており、書類が電子データで作成されたものであっても、プリントアウトして紙で保存・管理する必要がありました。
紙での保存・管理は、保管場所やコストの負担、情報の管理に関する負担など管理業務の非効率な問題がありました。このような業務の負担の軽減を図るために施行された法律が電子帳簿保存法です。
電子帳簿保存法は正式には「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」の名称で、1998年に制定されています。その後、規制や時代の変化に応じて2005年、2015年、2016年、2020年と改正が行われ規制の緩和がされております。
電子データの保存方法
電子帳簿保存法で認められている国税関係帳簿書類をデータで保存する方法は「電磁的記録による保存」と「スキャナ保存」の2種類があります。
電磁的記録による保存とは、各種書類を電子データのままでサーバやDVD、CDなどに保存する方法や、COMと呼ばれる「電子計算機出力マイクロフィルム」を使い、マイクロフィルムでデータを保存する方法です。
スキャナ保存は、紙の書類をスキャンすることで書類を電子データとして保存する方法です。2005年の電子帳簿保存法の改正された際にスキャナ保存制度として導入されております。
なお、それぞれの保存方法のうち、保存が認められている帳簿や書類の対象が異なります。
| 電磁的記録による保存 | スキャナ保存 | |
|---|---|---|
| 会計帳簿(総勘定元帳、仕訳帳など) | 〇 | × |
| 計算書類(貸借対照表、損益計算書など) | 〇 | × |
| その他国税関係書類(領収書、請求書、注文書など) | 〇 | 〇 |
電子データの保存要件
電子帳簿保存法では、帳簿書類の電子データを保存するにあたり、「真実性の確保」と「可視性の確保」の2つの要件をみたさなければならないと規定されております。
「真実性の確保」とは、帳簿書類の訂正や削除の事実内容が確認できること、タイムスタンプの付与や一定水準以上のスキャナーの解析度などの要件があげられます。
「可視性の確保」とは、システムやプログラムの開発関係書類などの備え付け、取引年月日・勘定科目・取引金額などの主要な記録項目で検索することができるなどが要件にあげられます。
それぞれの具体的な要件は、下記の内容になります。
| 真実性の確保 | ・データの訂正又は削除の履歴の保存 ・入力期間の制限、受領又は作成後、一定期間内又は適時にデータ化 ・タイムスタンプの付与、入力者等の情報の保存 ・スキャナ等の解析度要件、解像度、階調などの読取情報の保存 ・保存システム関係書類の備え付け 等 |
|---|---|
| 可視性の確保 | ・システム、プログラムの概要、データ保存に関する事務処理規定の備え付け ・帳簿と書類の相互関連性を通し番号や検索方法の設定 ・日付や金額で取引を検索できる機能(範囲指定、複数条件での検索) ・一定の要件を満たすカラーディスプレイなどの備え付け 等 |
電子帳簿保存を適用する場合には「真実性の確保」と「可視性の確保」の保存要件を満たす必要がありますので、システムの構築や運用を踏まえて事務処理の効率化と投資効果を合わせて検討が必要になります。
電子帳簿保存法の申請方法
電子帳簿保存を適用する手続きは、事前の申請が必要になります。所轄の税務署へ承認申請書と添付書類をそろえて申請します。
「電磁的記録等(電子データ)による保存」「スキャナーによる保存」「マイクロフィルムによる保存」と申請内容により申請書が分かれています。
提出期日は、電子帳簿保存を開始する日の3ヶ月前までになります。
| 税務署長への承認 | 「電子的記録による保存」「スキャナ保存」それぞれに承認が必要になります。電子帳簿保存を開始する日の3ヶ月前までに、税務署長に承認申請書と添付書類の提出が必要になります。 |
|---|
2020年改正のポイント
2020年に新たに改正された電子帳簿保存法の改正のポイントは、電子取引に重点が置かれ、電子マネーなどのキャッシュレス決済を利用した場合の紙の領収書が不要となり、経理処理がペーパーレス化できる点にあります。
これまでは経費になる領収書等は保存しておくことが必要でしたが、2020年の改正により、キャッシュレス決済やクレジットカード決済を利用した場合には、その取引明細のデータを保存することが可能になり、それぞれの取引明細のデータが領収書等の代わりになります。
また、これまで改ざん防止や不正防止のためにタイムスタンプを付与する必要がありましたが、今回の改正によりデータを自由に改変ができないシステムの利用について、タイムスタンプの付与が不要となりました。
なお、業務上、データの保存にクラウドサービスを利用している場合、保存期間や閲覧期間の制限がありますので、7年間の保存ができない場合には、取引明細のデータ等のダウンロードが必要になります。
その際、ダウンロードしたデータは、訂正や削除ができてしまうことから改ざん防止や不正防止のためにタイムスタンプの付与の対応は必要になります。
今後、電子帳簿保存法を活用することで、経理業務の効率化や経費処理の負担が軽減されるものと期待されます。
まとめ
中小企業や個人事業者は、事業に関する書類や会計帳簿を備え付けし、取引を記録して、保存する義務があります。
帳簿書類の記入や保存は手間がかかるだけでなく、書類の保管するスペースの確保や管理コストの負担もかかります。また、過去の帳簿書類の内容を確認することも、多大な労力を必要とされると思います。
電子帳簿保存法は制度が制定されてから改正を重ね、電子データの取り扱いが簡素化されてきました。電子帳簿保存法の活用を検討することで、経理業務の効率化やコスト削減、パーパレス化による生産性の向上も期待できます。
また、事業経営上のキャッシュレス化は、領収書や請求書のペーパレスによる電子データの保管・管理にも必要になりますので、電子帳簿保存法の把握も必要といえます。
関連するページのご紹介
こちらのページを読んだ方には、下記のサービスページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
お問い合せ・初回のご相談はこちら

税務・財務のご相談を受け付けております。
アクセス
住所
〒110-0005
東京都台東区上野3丁目16-2 413号
最寄り駅
・JR 御徒町駅より徒歩4分
・銀座線 上野広小路駅より徒歩4分
・大江戸線 上野御徒町駅より徒歩4分
・千代田線 湯島駅より徒歩4分
・京成線 京成上野駅より徒歩9分
・JR 上野駅より徒歩12分
営業時間
9:30~18:00
定休日
土曜日・日曜日・祝日