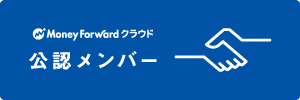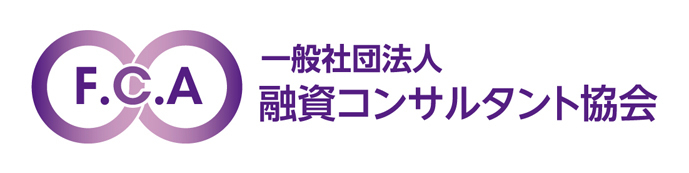お電話でのご依頼・お問い合せはこちら
年末調整の改正と電子化手続き
令和2年分の年末調整については、例年と異なる改正点が数多くあります。また、会社と従業員双方の年末調整に関する事務手続きを軽減することを目的として「年末調整手続きの電子化」が実施されます。
ここでは、2020年(令和2年)の年末調整で昨年までと異なる改正事項と年末調整の手続きの電子化について説明します。
《目次》
1.給与所得控除に関する改正
2.基礎控除に関する改正
3.子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設
4.各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件の改正
5.ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正
6.年末調整の電子化の概要
7.年末調整の電子化へ向けた具体的な準備
8.まとめ
給与所得控除に関する改正
給与所得控除額が下記の表のとおりに改正されました。
| 給与の収入金額(A) | 給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 改正後 | 改正前 | |
| 162万 5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万 5,000円超 180万円以下 | (A)×40%ー10万円 | (A)×40% |
| 180万円超 360万円以下 | (A)×30%+8万円 | (A)×30%+18万円 |
| 360万円超 660万円以下 | (A)×20%+44万円 | (A)×20%+54万円 |
| 660万円超 850万円以下 | (A)×10%+110万円 | (A)×10%+120万円 |
| 850万円超 1,000万円以下 | 195万円 | |
| 1,000万円超 | 220万円 | |
この改正により、「年末調整等のための給与所得控除額の給与等の金額の表」が改正されております。
基礎控除に関する改正
基礎控除額が下記の表のとおり改正されました。
この改正により、合計所得金額が2,500万円を超える所得者については、基礎控除の適用を受けることができないこととされております。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 | |
|---|---|---|
| 改正後 | 改正前 | |
| 2,400万円以下 | 48万円 | 38万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | |
基礎控除額は、改正前において所得基準はありませんでしたが、今回の改正で所得基準に応じて基礎控除額が変更になります。
合計所得金額が2,400万円以下の所得者の基礎控除額は、これまでの38万円から48万円へと10万円増える一方、合計所得金額が2,500万円を超える所得者については、基礎控除の適用を受けることができなくなります。
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設
その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者で、次の①から④のいずれかに該当する場合に、給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額(最高15万円)を、給与所得の金額から控除することとされます。
①所得者本人が特別障害者
②同一生計配偶者が特別障害者
③扶養親族が特別障害者
④扶養親族が年齢23歳未満(平成10年1月2日以後生)
基礎控除の改正及び所得金額調整控除の創設によって、それぞれ「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」が新たに設けられました。
年末調整で基礎控除又は所得金額調整控除の適用を受けようとする場合には、その年の最後に給与の支払いを受ける日の前日までにそれぞれ「給与所得者の基礎控除申告書」又は「所得金額調整控除申告書」を給与の支払者(会社又は事業者)へ提出が必要になります。
各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件の改正
同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられました。
それぞれの改正の内容は、下記の表のとおりになります。
| 扶養親族等の区分 | 合計所得金額要件 | |
|---|---|---|
| 改正後 | 改正前 | |
| 同一生計配偶者 | 48万円以下 | 38万円以下 |
| 扶養親族 | 48万円以下 | 38万円以下 |
| 源泉控除対象配偶者 | 95万円以下 | 85万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 48万円超 133万円以下 | 38万円超 123万円以下 |
| 勤労学生 | 75万円以下 | 65万円以下 |
配偶者特別控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分についても、それぞれ10万円引き上げられています。
上記のほかに、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円(改正前:65万円)に引き下げられています。
ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正
所得者がひとり親である場合で、次の①から③の要件を満たす場合には、ひとり親控除として、その人のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から35万円を控除することとされます。
①所得者と生計を一緒にする子がいること
②所得者の合計所得金額が500万円以下であること
③所得者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
*ひとり親とは、現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない人で上記の①から③の要件を満たす人のことをいいます。
寡婦控除の要件につきましても、上記②と③の要件が追加され、寡婦(寡夫)控除をひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除に改組されています。
なお、「特別の寡婦」に該当する場合の寡婦控除の特例は廃止されております。
年末調整の電子化の概要
従来の年末調整の手続きは、
①従業員が保険会社、金融機関等から書面で各種控除証明書等を取得
②従業員がこの控除証明書等をもとに、保険料控除申告書や住宅ローン控除申告書などに記載記載内容を転記して、控除額の計算
③従業員が控除証明書等と年末調整の際に作成した各種控除申告書など合わせて勤務先へ提出
④勤務先が提出された書類をチェックして年末調整の年税額の計算
という流れで進められいました。
電子化による年末調整の手続きは、
①従業員が保険会社等から電子データで控除証明書等を取得
②従業員は、国税庁のホームページ等からダウンロードした年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)に、①で取得した電子データを「年調ソフト」に取り込み、年末調整控除申告書の電子データを作成
③従業員が①の控除証明書等のデータと②の年末調整控除申告書のデータを勤務先に提出
④勤務先が③で提出された電子データを給与システム等にインポートして年末調整の計算
という手続きの手順になります。年末調整書類は、そのまま電子データで保管することになります。
なおここでの、「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)」とは、年末調整の申告書類について、控除証明書等のデータを利用して年末調整申告書の電子データを作成するもので、国税庁が無償で提供するソフトウェアになります。
年末調整の電子化へ向けた具体的な準備
年末調整の電子化へ向けて会社側、従業員側でそれぞれ準備対応が必要になります。それぞれ事前の準備内容について下記の内容になります。
| 企業おける準備 | ①電子化の実施方法の検討 | 使用するソフト・システム等の検討、電子化後の年末調整手続きの事務手順の検討が必要となります。 |
|---|---|---|
| ②従業員への周知 | 控除証明書等を電子データで準備する旨や、年末調整の事務手順等を事前に周知する必要があります。 | |
| ③給与システム等の改修等 | 従業員から提出された控除証明書等データや控除申告書等のデータをインポートし年末調整計算するために、給与システム等の改修等が必要となります。 | |
| ④税務署への届出 | 事前に所轄税務署長に「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書(以下「電磁的方法による提供の承認申請書」)を提出して、承認を受ける必要があります。 | |
| 従業員における準備 | ①年調ソフトの取得 | 保険会社や金融機関等から取得する控除証明書等のデータを利用して、年末調整申告データを作成するためのソフトを取得します。国税庁のものと、民間のものと、いずれを利用するかについては勤務先に確認します。 |
| ②控除証明書等のデータによる取得 | 保険会社や金融機関等のホームページ等からそれぞれの控除証明書のデータを取得します。 | |
| ③「マイナポータル連携」の利用検討 | マイナンバーカードを取得し、マイナポータルを開設活用することで、②によらず、控除証明書等の必要書類データを一括取得し、各種申告書への自動入力が可能となります。この機能を「マイナポータル連携」といいます。 |
まとめ
税制改正の影響を踏まえて、令和2年分の年末調整は従来と比べて改正事項が数多くあります。
控除の判定や控除額の変更は年税額の計算へも影響が生じますので、昨年までと変更になった点を踏まえて、概要を理解しておくと年末調整の業務が、少しでもスムーズに進められると思います。また、新設された申告書もありますので、従業員へも事前の周知が必要となります。
また、電子化によるデータ管理・運用も始まりますので、導入する際には事前の対応も必要になります。
関連するページのご紹介
こちらのページを読んだ方には、下記のサービスページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
お問い合せ・初回のご相談はこちら

税務・財務のご相談を受け付けております。
アクセス
住所
〒110-0005
東京都台東区上野3丁目16-2 413号
最寄り駅
・JR 御徒町駅より徒歩4分
・銀座線 上野広小路駅より徒歩4分
・大江戸線 上野御徒町駅より徒歩4分
・千代田線 湯島駅より徒歩4分
・京成線 京成上野駅より徒歩9分
・JR 上野駅より徒歩12分
営業時間
9:30~18:00
定休日
土曜日・日曜日・祝日