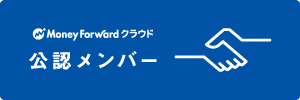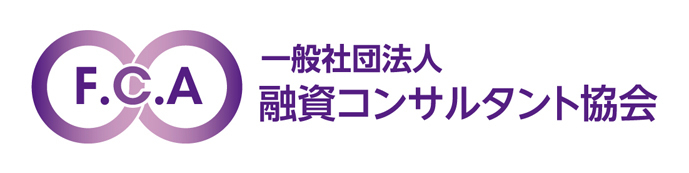お電話でのご依頼・お問い合せはこちら
準確定申告の申告の流れ

相続が発生した場合、被相続人の代わりに相続人が行う確定申告を準確定申告といいます。
準確定申告は、相続の発生した日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税を行う必要があります。
ここでは、準確定申告の申告手続きの流れ、具体的な内容について説明します。
《目次》
1.準確定申告とは
2.準確定申告の手続きの流れ
3.準確定申告の申告義務がある人
4.準確定申告で還付となる場合
5.準確定申告と納税が期限までに間に合わない場合のペナルティ
6.相続税の申告との関係
7.まとめ
準確定申告とは
所得税の確定申告は通常、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算して、翌年の2月16日から3月15日までに申告と納税をすることになっています。
年の途中で亡くなった人の場合は、相続人が1月1日から亡くなった日までに確定している所得について確定申告を行う手続が、準確定申告といいます。
準確定申告で提出する申告書は、一般の確定申告に準じた確定申告書として「準確定申告書」といいます。
また、被相続人が前年分の確定申告を行う前(3月15日まで)に亡くなった場合は、前年分と本年分の準確定申告が必要になります。
この時、前年分の準確定申告の期限も相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内が申告の期限になります。
例えば、被相続人が前年分の確定申告を行わないで2月20日に亡くなった場合は、準確定申告の期限が前年分・本年分とも6月20日が申告の期限になります。
準確定申告の手続きの流れ
準確定申告では、その年の1月1日から亡くなりになる日までの所得税について相続人が申告と納税の一連の手続きを行います。
準確定申告の申告期限は、相続発生の日の翌日から4ヶ月以内です。所得税の納付期限につきましても、申告期限と同じになります。
準確定申告書の提出先は、被相続人の亡くなられた時の住所地を管轄する税務署になります。その際に、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄、法定相続分などを記載した「死亡した者の所得税の確定申告書付表」の書類も申告書に添付して提出します。
また、被相続人が個人事業として事業を行われていた場合は、個人事業の開業・廃業等届出書を相続があった日から1ヶ月以内に、消費税の申告をしていた場合には、消費税における個人事業者の死亡届出書も合わせて提出が必要になります。
なお、準確定申告を申告することで所得税の還付を受ける場合には、4ヶ月以内の期限はありません。税金還付請求できる5年以内に申告することで、還付を受けることができます。
準確定申告の申告義務がある人
準確定申告は、亡くなったすべての人が申告の対象となるものではありません。
準確定申告の申告義務がある人は、毎年、確定申告して所得税を納めていた場合や源泉された税額よりも納める所得税が多い場合など、準確定申告で納税すべき所得税がある人が必要になります。
具体的に、被相続人が次に該当する場合、準確定申告の申告が必要となることが考えられます。
・給与収入が年間2,000万円を超えていた場合
・給与収入が2カ所以上からある場合
・給与収入以外(副業等)の所得が20万円を超えていた場合
・不動産(土地・建物)を売却した場合
・株式の取引があり、源泉徴収がされていない場合
・事業を行っていた場合
・不動産の賃貸を行っていた場合
被相続人がこれらに該当する場合は、準確定申告の申告の義務が考えられます。
毎年、確定申告を行っていた場合には、過去の申告書から申告の内容を確認することも参考になります。
準確定申告で還付となる場合
準確定申告書を申告することで、所得税の還付となる場合もあります。
還付の場合は、準確定申告の義務ではなく、還付を受けるための申告として還付申告といわれます。
還付の場合でも準確定申告の申告を行わないと所得税は還付されません。
具体的に、被相続人が次に該当する場合、準確定申告で還付されると考えられます。
・年の途中で退職して、年末調整を受けていない給与収入がある場合
・亡くなる前までの間に10万円を超える医療費を支払っている場合
・各種所得控除(寄付金控除、雑損控除)がある場合
・源泉徴収されており、控除しきれない所得税がある場合
・所得税の予定納税ある場合で、控除しきれない所得税がある場合
準確定申告と納税が期限までに間に合わない場合のペナルティ
申告期限までに必要な手続きが間に合わず、申告手続きが遅れた場合や納税が遅れてしまう場合は、罰則としてペナルティがかかります。
罰則としてのペナルティは、申告を行わなかったことによる無申告加算税と納税が遅れたことよる延滞税になります。
| 無申告加算税 | 無申告加算税は申告が必要な場合、申告期限までに申告をしなかったことに対してかかります。 ペナルティ的な性格で、申告によって支払うべき所得税に対して加算されます。 税率は、申告期限を過ぎて税務調査を受ける前に自主的に申告した場合と、税務調査を受けてから申告した場合とで率が異なります。 |
|---|---|
| 延滞税 | 延滞税は申告期限までに、納付しなかった所得税に対してかかります。利子的な性格になります。 税率は期間に応じて、税額は本来の納付期限の翌日から相続税を納付した日までの日数に応じて計算されます。
|
〇無申告加算税の税率
| 相続税の税額のうち | 税務調査の事前通知より前に自主的に申告した場合 | 税務調査の事前通知を受けてから税務調査を受けるまでに申告した場合 | 税務調査を受けてから申告した場合* |
|---|---|---|---|
| 50万円以下の部分 | 5% | 10% | 15% |
| 50万円超の部分 | 15% | 20% |
*過去5年以内に所得税で無申告加算税または重加算税が課されたことがあるときは、税率が10%加算されて、50万円以下の部分は25%、50万円超の部分は30%になります。
〇延滞税の税率
| 期 間 | 納期限の翌日から2月を経過するまで | 納期限の翌日から2月を経過した日以後 |
|---|---|---|
| 2021年1月1日から2021年12月31日 | 年2.5% | 年8.8% |
| 2020年1月1日から2020年12月31日 | 年2.6% | 年8.9% |
| 2019年1月1日から2019年12月31日 | 年2.6% | 年8.9% |
| 2018年1月1日から2018年12月31日 | 年2.6% | 年8.9% |
| 2017年1月1日から2017年12月31日 | 年2.7% | 年9.0% |
| 2016年1月1日から2016年12月31日 | 年2.8% | 年9.1% |
| 2015年1月1日から2015年12月31日 | 年2.8% | 年9.1% |
延滞税は所得税の本税部分のみを対象としてかかり、無申告加算税にかかりません。
相続税の申告との関係
準確定申告で所得税の還付を受けた場合、この還付金は相続財産として相続税の課税の対象となります。
相続税の申告が必要となる場合には、早めに準確定申告を行うことが必要になります。
なお、還付される際に、利子部分の還付加算金が付加される場合がありますが、この還付加算金については、相続税の課税計算の対象にはなりません。
還付加算金は、還付金を受け取った相続人の所得税の対象となります。支払いを受ける還付加算金は、所得税の計算上、雑所得として取り扱われます。
まとめ
相続が発生してから必要となる税務申告は相続税の申告以外にも、被相続人の所得税の確定申告が必要な場合、準確定申告の申告と納税の手続きが必要になります。
申告と納税には申告期限が設けられているため、相続税の申告や各相続手続きと合わせてスケジュールを進めていくことが大切です。
準確定申告が必要かどうか、被相続人がお亡くなりになる前までの収入状況をまずは確認してから、申告が必要かどうか判断することがポイントです。また毎年、確定申告を行っていた場合、過去の申告書の控えから収入内容を確認することも参考となります。
相続税の申告では相続税の負担を軽減する制度があります。こうした制度を適用して申告、税金の計算を行うことで相続税の節税効果にもつながります。
相続税の申告でお困りやお悩みがありましたら、ご相談ください。
関連するページのご紹介
こちらのページを読んだ方には、下記のサービスページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
お問い合せ・初回のご相談はこちら

税務・財務のご相談を受け付けております。
アクセス
住所
〒110-0005
東京都台東区上野3丁目16-2 413号
最寄り駅
・JR 御徒町駅より徒歩4分
・銀座線 上野広小路駅より徒歩4分
・大江戸線 上野御徒町駅より徒歩4分
・千代田線 湯島駅より徒歩4分
・京成線 京成上野駅より徒歩9分
・JR 上野駅より徒歩12分
営業時間
9:30~18:00
定休日
土曜日・日曜日・祝日