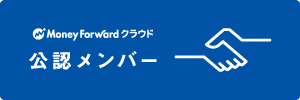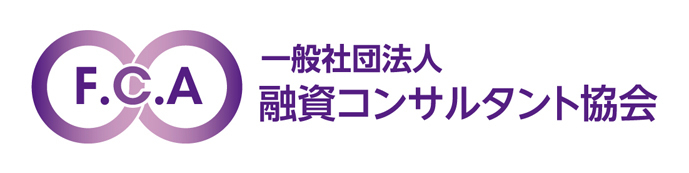お電話でのご依頼・お問い合せはこちら
配偶者の税額軽減

相続税の計算でいくつも相続税控除制度が設けられています。
その中の一つに配偶者の相続税の税負担を軽減する制度があります。
この制度は、被相続人の配偶者に対する優遇制度で、被相続人の相続後の配偶者の生活の負担を減らすことや、夫婦間での財産の形成において少なからず配偶者の貢献も考慮した制度として設けられています。
ここでは、相続税の配偶者の税額軽減について具体的に説明します。
《目次》
1.配偶者の税額軽減とは
2.配偶者の税額軽減を受ける手続き
3.相続税の申告期限までに遺産が未分割の場合
4.二次相続を含めた相続対策
5.まとめ
配偶者の税額軽減とは
配偶者の税額軽減とは、亡くなった人の配偶者が遺産分割や遺贈により相続した遺産の額が以下の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
●1憶6,000万円
●配偶者の法定相続分相当額
配偶者が相続した遺産の総額が1憶6,000万円までであれば、配偶者に相続税が課税されません。また、1憶6,000万円を超えても、配偶者の法定相続分までであれば、相続税が課税されません。
配偶者の税額軽減の適用を受けることができる配偶者は、被相続人が亡くなった時点で法律上の婚姻関係にある配偶者に限られます。
そのため、内縁関係のある事実上の配偶者や、被相続人が亡くなる前に離婚届を提出した元配偶者は、仮に、遺言等で財産を相続したとしても、配偶者の税額軽減の適用は受けることができないため注意が必要です。
法律上の婚姻関係であることが要件のため、婚姻関係を継続していて別居中の場合や、離婚調停中である場合でも、配偶者の税額軽減の適用は受けることができます。
配偶者の税額軽減を受ける手続き
配偶者の税額軽減は減税を活用できる制度ですが、適用をうけるためには必ず相続税の申告書を税務署へ提出する手続きが必要です。
配偶者の税額軽減の適用を受けて、納付する納税額が0円の場合でも申告手続きは必要になります。
配偶者の税額軽減を受けるためには、相続税の申告期限までに、申告書に税額軽減の明細を記載した「配偶者の税額軽減額の計算書」を添付して申告を行う必要があります。
また、申告書類と合わせて、戸籍謄本と遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど取得した財産が分かる書類も合わせて添付が必要です。
相続税の申告期限までに遺産が未分割の場合
相続税の申告期限までに相続財産の分割方法が決まらないというケースもありえます。
その場合でも一定の手続きを行うことで配偶者の税額軽減の適用を受けることができます。
具体的には、相続税の申告の際に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告を行います。
この見込書を提出することで、申告期限から3年以内に分割した遺産についても、あらためて申告をし直すことで配偶者の税額軽減の対象とされます。
もし、3年の期限を経過してもやむを得ない事情で遺産の分割協議がまとまらない場合には、税務署長の承認を受けて猶予を受けることができます。やむを得ない事情がなくなった日の翌日から4ヶ月以内に遺産分割協議が完了すれは、配偶者の税額控除を受けることが可能です。
二次相続を含めた相続対策
配偶者の税額軽減制度を適用することで、配偶者の相続税の負担を軽減して被相続人の遺産を相続することができます。法定相続分より遺産相続の額を増やしたとしても配偶者の税額軽減により相続税の納税額を軽減することができます。
被相続人の遺産総額が大きい場合には、配偶者にとって配偶者の税額軽減は節税の効果がある制度です。
このように夫婦のどちらかが亡くなる一次相続の場合には、配偶者の税額軽減で税額の節税効果は期待されます。ただし、一次相続で相続税の負担が軽減されたとしても二次相続の時には配偶者の税額軽減の税額控除は適用できないため、多額の相続税が生じる可能性も考えられます。相続人である子どもなどへの納税負担が大きくなることも想定されます。
実際に相続が発生した時は、二次相続のこともふまえて、一次相続の時点でどのように遺産を分割していくか、トータルの納税額をシミュレーションして検討しておくことが必要です。
一次相続前の生前贈与も検討しながら、財産の承継を図ることが相続対策になります。
まとめ
相続税の配偶者の税額軽減は、亡くなった人の配偶者が相続した遺産の総額の1憶6,000万円と法定相続分のいずれか多い金額までは相続税が非課税とされます。遺産総額が大きい場合には、配偶者の税額軽減を適用することで相続税の節税の効果があります。
ただし、一次相続の税負担だけを考え配偶者に遺産を集約して相続すると、次の二次相続では、配偶者の税額軽減が適用されないことや相続人が一人減り基礎控除額が減ることで、大きく相続税が課税される可能性も考えられます。
配偶者のこれからの生活や財産形成を考慮しながら、二次相続までの相続税のシミュレーションを行い税負担の納税予測を把握することが重要です。いつ、だれが、どの財産を、どれだけ相続していくかタイミングとバランスを考えて決めることが相続財産の承継の上で大切といえます。
相続税の申告では相続税の負担を軽減する制度があります。こうした制度を適用して申告、税金の計算を行うことで相続税の節税効果にもつながります。
相続税の申告でお困りやお悩みがありましたら、ご相談ください。
関連するページのご紹介
こちらのページを読んだ方には、下記のサービスページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
お問い合せ・初回のご相談はこちら

税務・財務のご相談を受け付けております。
アクセス
住所
〒110-0005
東京都台東区上野3丁目16-2 413号
最寄り駅
・JR 御徒町駅より徒歩4分
・銀座線 上野広小路駅より徒歩4分
・大江戸線 上野御徒町駅より徒歩4分
・千代田線 湯島駅より徒歩4分
・京成線 京成上野駅より徒歩9分
・JR 上野駅より徒歩12分
営業時間
9:30~18:00
定休日
土曜日・日曜日・祝日