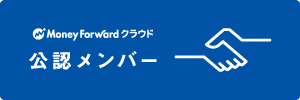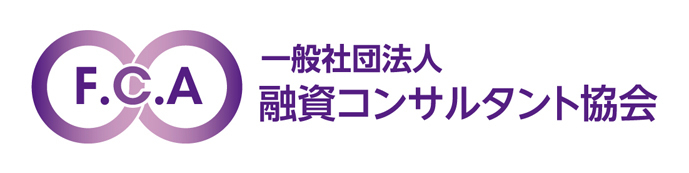お電話でのご依頼・お問い合せはこちら
令和5年度 税制改正大綱の解説

令和4年12月16日に令和5年度の税制改正の大綱が公表されました。
税制改正の大綱においては、2,000兆円に及ぶ個人金融資産、500兆円に及ぶ企業の内部留保、3,000万人を超える旅行客を呼び込んだ全国の地域の資源など、個人や企業、そして地域に潜在する成長を最大限に引き出すとのメッセージをもとに税制改正が発表されています。
具体的に、「マーケット」「産業」「人材」への成長投資を一体的に強化することで、成長と分配の好循環の実現をかかげて策定されています。家計の資産を貯蓄から投資へと積極的に振り向け、また、資産課税において経済社会の構造変化による資産移転の中立な税制の措置、スタートアップ・エコシムステムを抜本的に強化するための税制の措置などがかかげられています。
主要な改正内容として、所得税では、個人投資家の優遇制度「NISA」の抜本的な拡充と恒久化、スタートアップへの再投資にかかる非課税措置の創設。資産税では、贈与の暦年課税における相続前3年分を加算するとされていた期間が7年に延長され、相続時精算課税制度を適用する場合において110万円までの基礎控除が創設されます。
その他、消費税のインボイス制度の開始に伴う見直しや電子帳簿保存法の改正も盛り込まれています。
改正内容のうち、個人の家計、中小企業や個人事業者、資産税に関連する改正事項を中心に解説いたします。
《目次》
1.個人所得課税
2.資産課税
3.法人課税
4.消費課税
5.納税環境整備
6.まとめ
個人所得課税
NISA(少額投資非課税制度)の抜本的な拡充と恒久化
NISA(少額投資非課税制度)が2024年(令和6年)1月から拡充されます。
制度の恒久化とともに非課税で投資できる期間を無制限にして、投資額の枠も広がります。
投資額の枠は年間最大360万円まで、生涯の投資額の枠は1,800万円の範囲内で利用ができるようになります。
「一般NISA」は「成長投資枠」に替わり、年間の投資額を現在改正前の120万円の2倍の年240万円までの投資額の枠に拡大し、「つみたてNISA」は現在改正前の40万円の3倍の年120万円まで投資額の枠を広げます。
生涯の投資額の枠を合計1,800万円まで設け、そのうち成長投資枠は1,200万円を上限とされます。
制度の恒久化として、配当や分配金、譲渡益に税金がかからずに投資できる期間を無期限と改正されます。
今までは、「一般NISA」が5年間、「つみたてNISA」は20年間の非課税の期間が設けられていました。
具体的には、下記の一覧表が改正内容になります。
| 改正項目 | 改正前 | 改正後 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一般NISA | つみたてNISA | 成長投資枠 | つみたてNISA | |
| 年間投資額 | 120万円 | 40万円 | 240万円 | 120万円 |
| 非課税限度額 | 600万円 | 800万円 | 1,800万円 (成長投資枠はうち1,200万円) | |
| 対象商品 | 上場株式 投資信託等 | 一定の投資信託 | 上場株式 投資信託等 | 積立・分散投資に適した 一定の投資信託 |
| 対象年齢 | 18歳以上 | 18歳以上 | ||
| 投資期間 | 5年間 | 20年間 | 無期限 | |
*2024年(令和6年)1月から適用されます。
スタートアップへの再投資にかかる非課税措置の創設
個人が保有する株式を売却してスタートアップへ再投資する場合に、再投資した金額につき20億円を上限として、株式の売却益に課税しない制度が創設されます。
| 対象となるスタートアップの主な要件 |
|---|
| ・設立の日以後、1年未満の中小企業者であること |
| ・販売費及び一般管理費の出資金額に対する割合が30%を超えること |
| ・特定の株主グループが発行済株式の総数の99%を超える保有をしていないこと |
| ・金融商品取引所に上場されている株式等の発行者である会社でないこと |
| ・大規模法人の子会社等ではないこと |
| ・風俗営業などの事業を行う会社ではないこと |
高所得者層に対する課税の強化
極めて所得が高い水準の個人に対して所得税の課税が強化されます。
その年の給与所得、事業所得、株式の譲渡所得、土地建物の譲渡所得、その他の各種の所得を合算した所得金額(基準所得金額)から3億3,000万円を控除した金額に、22.5%の税率を乗じた金額が、その年の納める所得税の金額を超える場合、その超える金額を追加して納めることとされます。
《改正のポイント》
具体的な所得税の計算は、
① 所得税額
②(基準所得金額 - 特別控除額 3億3,000万) × 22.5%
②の金額が①の金額を超えた場合、その差額を申告して納めることになります。
*2025年(令和7年)以後の所得税について適用されます。
資産課税
生前贈与の相続財産加算期間の延長
暦年贈与により生前に贈与を受けていた財産について、相続時に加算される贈与の期間が相続前3年以内から相続前7年以内に延長されます。
ただし、延長された4年間の贈与について総額100万円までは相続財産に加算しない措置がとられます。
*2024年(令和6年)1月1日以後の贈与から適用されます。
相続時精算課税制度について毎年110万円の基礎控除を創設
相続時精算課税制度により行われた贈与について、現行の基礎控除とは別に、贈与の課税価格から毎年110万円の基礎控除ができるようになります。
また、相続税の計算において加算される価格も、贈与財産の価格から過去の基礎控除額を控除した後の金額になります。
*2024年(令和6年)1月1日以後の贈与による財産の相続税と贈与税から適用されます。
相続時精算課税制度による贈与財産が災害によって被害を受けた場合の再計算
相続時精算課税制度により行われた贈与の後に、贈与財産の土地や建物が災害によって一定の被害を受けた場合、相続税の計算において加算される価格は、贈与の時の財産の価格から災害を受けた金額を控除した金額とされます。
*2024年(令和6年)1月1日以後に生じた災害によって被害を受けた場合から適用されます
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直しと延長
教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期間が3年間延長されます。
また、契約期間中に贈与者が死亡した場合で、贈与者の相続税の課税価格が5億円を超える場合には、受贈者の年齢にかかわらず非課税拠出金の残高を相続財産に加算されることになります。
*2023年(令和5年)4月1日以後に取得する信託受益権等の贈与税に適用されます。
結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置の見直しと延長
結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期間が2年間延長されます。
また、契約終了時に非課税拠出額の残高がある場合の贈与税の税率は、本則の一般税率を適用することとされます。
*2023年(令和5年)4月1日以後に取得する信託受益権等の贈与税に適用されます
《改正のポイント》
暦年贈与による相続時の生前贈与の加算の対象年度が、これまでの3年から7年に変更されました。
暦年贈与による生前贈与の加算制度では、相続時に加算される際に、基礎控除額が控除されなくなる一方で、相続時精算課税では基礎控除額が控除されるため、相続前7年間の贈与については暦年贈与より相続時精算課税が節税対策になります。
基礎控除額を利用した相続対策を行う場合に、相続時精算課税の選択が以前よりも選択しやすい制度に改正されています。
法人課税
中小企業投資促進税制等の見直し
中小企業の優遇税制である中小企業投資促進税制(7%税額控除・30%特別償却)と中小企業経営強化税制(10%税額控除・100%即時償却)の対象資産から、一定のコインランドリー設備と暗号資産のマイニング機械装置の設備が対象から除外されることになります。
| 改正内容 | |
|---|---|
| 中小企業投資促進税制 | 中小企業投資促進税制の対象設備からコインランドリー業(主要な事業でない場合)の機会装置で、その管理を外部へ委託するものを対象資産から除外されることになります。 |
| 中小企業経営強化税制 | 中小企業経営強化税制の対象資産からコインランドリー業又は暗号資産マイニング業(主要な事業でない場合)の機械装置で、その管理を外部へ委託するものを対象資産から除外されることになります。 |
*2025年(令和7年)3月31日までの間に事業の用に供した資産に適用されます。
《実務のポイント》
近年、法人税の行き過ぎた節税や課税の繰り延べの防止策として措置が入る傾向があることから、過度な節税商品や課税の繰り延べ商品には注意が必要です。
研究開発税制の見直し
研究開発税制は、研究開発を行う企業が、研究開発に係る試験研究費の一定割合を法人税から控除できる制度です。
研究開発投資の規模拡大や開発の質の向上のため、研究開発税制について見直しが行われています。
具体的には、控除率カーブの見直しと税額控除率の下限が引き下げられ(現行の2%から1%へ引き下げ)、また、試験研究費の額が大きい企業に対してインセンティブの強化に試験研究費の増減割合に応じてた税額控除の上限を変動される制度が設けられます。
試験研究費の対象となる範囲についても、新たなサービス開発を促すためにも、既存のビッグデータを活用したサービス開発も対象に含まれるようになります。
ただし、今まではデザインに基づく「設計・試作」であって、性能向上を目的としていなくても試験研究費の対象とされていましたが、性能向上を目的としないことが明らかな「設計・試作」は、試験研究費の対象の範囲から除かれることになります。
*2024年(令和5年)4月1日から2026年(令和8年)3月31日までの間に開始する事業年度から適用されます。
オープンイノベーション促進税制の拡充
特別新事業開拓事業者(スタートアップ企業)に対して特定事業活動として出資した株式を発行法人以外の者から取得した場合でも、株式取得価額の25%の所得控除が可能となります。
特定株式の取得から5年以内の成長率や投資規模等の要件を満たした場合、減税メリットを継続する仕組みに見直されます。
消費課税
適格請求書等保存方式の実施に向けた小規模事業者に対する負担軽減措置
今まで免税事業者であった中小企業や個人事業者が、インボイス発行事業者になった場合の消費税の納付税額を売上に係る消費税額の2割の金額に軽減することとされます。
この消費税の負担軽減措置の適用期間は、3年間の期限が設けられています。
*対象となる課税期間は、2023年(令和5年)10月1日から2026年(令和8年)9月30日までの日に属する課税期間に適用されます。
| 適用対象とされる中小企業や個人事業者 下記のいずれかに該当するインボイス発行事業者が対象とされます |
|---|
| ・免税事業者である中小企業や個人事業者が、適格請求書発行事業者になった場合 |
| ・課税事業者選択届出書を提出したことにより、課税事業者になった場合 (基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるインボイス発行事業者が対象) |
インボイス発行事業者が、この負担軽減措置の適用を受けようとする場合には、消費税の確定申告書に適用を受ける旨を付記するだけで適用が受けられます。
《実務のポイント》
現状、消費税の計算方法は、原則課税と簡易課税の選択により計算方法の適用が認められていますが、適格請求書等保存方式の実施に向けた小規模事業者の負担軽減措置の選択により計算方法の選択も3通りに増えます。
今まで免税事業者であった中小企業や個人事業者がインボイス発行事業者を選択する場合には、業績数値を踏まえま上で、消費税の負担が少なくなる詳細なシミュレーションも事前に必要と考えられます。
適格請求書等保存方式の実施に向けた事務負担の軽減措置
一定の中小企業者は、対価が1万円未満の課税仕入について、インボイスの保存がなくても帳簿の記載による保存のみで仕入税額控除の適用が認められます。
この事務負担の軽減措置の適用期間は、6年間の期限が設けられています。
*適用される期間は、2023年(令和5年)10月1日から2029年(令和11年)9月30日までの間に行う課税仕入に適用されます。
| 適用対象とされる事業者 下記のいずれかに該当する事業者が対象とされます |
|---|
| ・基準期間における課税売上高が1億円以下である事業者 |
| ・特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者 |
《実務のポイント》
改正によるインボイスの保存が不要となる取引は、一定の中小企業者で税込み1万円未満の課税仕入れに限られます。
基準期間の売上高が1億円を超える事業者は、1万円未満の取引についてもすべてのインボイス番号の確認と書類の保存が必要になります。
クレジットカード決済した経費などについてもすべてのインボイスの保存が必要になるため、インボイス番号の確認や保存の管理など社内でのオペレーション対応が必要と考えられます。
適格請求書等保存方式の少額な返還インボイスの交付義務の見直し
売掛金の入金の際に、差し引かれる振込手数料について「値引き」として返還インボイスの交付義務が必要でしたが、税込金額が1万円未満の売上返還については、返還インボイスの交付義務が不要とされます。
*2023年(令和5年)10月1日以後の売上返還の取引から適用されます。
納税環境整備
電子帳簿等保存制度の見直し
電子取引の取引情報に関する電磁的記録の保存制度について、事業者側の負担軽減や電子化の促進から要件緩和の改正が行われます。
電子取引で受け取った請求書等の電子データについて、取引年月日、取引先、取引金額で検索できる検索要件につき、下記のいずれかに該当する事業者は、検索要件が不要とされます。
| 検索要件が不要とされる事業者 |
|---|
| ・判定期間(法人の場合は前々事業年度、個人事業者の場合は前々年)における売上高が5,000万円以下である事業者 |
| ・電子取引の出力書面が取引年月日や取引先ごとに整理がされていて、書面の提示または提出の求めに応じることができるようししている事業者 |
電子取引による請求書等のデータは紙ではなく電子データの保存が義務化されましたが、今回、電子取引を要件に従って保存することができない「相当の理由」があると認められる事業者については、電子データのダウンロードに応じることができ、電子取引の出力書面の提示または提出に応じることができれば、電子帳簿保存法の要件を満たすこととされます。
実質的には、「相当の理由」があるとみと認められる場合、電子取引のデータの保存と請求書等の電子取引のデータを印刷して保存することで要件が満たされることになります。
*適用時期は、2024年(令和6年)1月1日以後の電子取引の電子データ保存から適用されます。
無申告加算税の割合の引き上げ
無申告加算税について、納付すべき税額が300万円を超える場合、300万円を超える部分に対する無申告加算税の税率が30%に引き上げられます。
現行では、納付すべき税額が50万円までは無申告加算税は15%、納付すべき税額が50万円を超える部分の無申告加算税は20%です。
*適用時期は、2024年(令和6年)1月1日以後に法定期限に申告される国税について適用されます。
まとめ
令和5年度の税制改正の内容のうち、個人の家計、中小企業・個人事業者の経営、資産税に関連する改正事項を中心に解説しました。
個人に関する改正では、NISAの投資額の拡充と非課税期間を無期限により、家計の資産を投資へと振り向ける改正の内容となっています。
資産税関連では、「相続税と贈与税の一本化」への課税の見直しとして以前から話題にあがっていました贈与税の改正があり、今後の相続対策において改正の制度も踏まえての検討が必要になります。
また、中小企業や個人事業者にとって、消費税のインボイス制度の軽減措置や電子帳簿保存法の改正のデータ保存の義務にも、導入開始前に事前の再検討や選択が必要といえます。
今回の改正で具体的な取り決めは行われませんでしたが、次年度以降で防衛力強化に係る財源確保のための税制措置が行われる予定です。具体的に、法人税に対して税率4%~4.5%の付加税、所得税に対して税率1%の付加税、たばこ税の引き上げの措置が検討されています。
また、外形標準課税のあり方の検討、マンションの相続税評価の検討があげられ、今後の課題として検討を行う方針にありますので、来年度以降の税制改正で注視される項目と考えられます。
関連するページのご紹介
こちらのページを読んだ方には、下記のサービスページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
お問い合せ・初回のご相談はこちら

税務・財務のご相談を受け付けております。
アクセス
住所
〒110-0005
東京都台東区上野3丁目16-2 413号
最寄り駅
・JR 御徒町駅より徒歩4分
・銀座線 上野広小路駅より徒歩4分
・大江戸線 上野御徒町駅より徒歩4分
・千代田線 湯島駅より徒歩4分
・京成線 京成上野駅より徒歩9分
・JR 上野駅より徒歩12分
営業時間
9:30~18:00
定休日
土曜日・日曜日・祝日