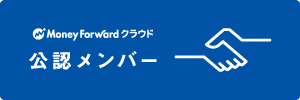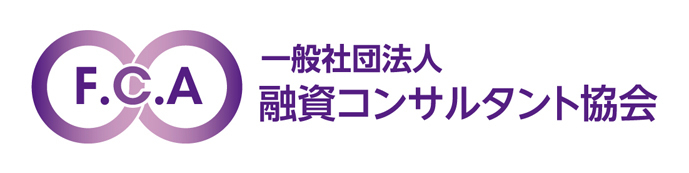お電話でのご依頼・お問い合せはこちら
相続税の負担が軽くなる小規模宅地等の特例

相続税の税制のメリットで、課税価格の計算の特例が設けられています。
相続財産に土地が含まれている場合、小規模宅地等の特例の適用が受けられると、一定の限度面積まで土地の評価額を減額することができます。
この制度は、土地の評価に対する優遇制度で、相続する土地の評価額を最大80%まで減額することができます。
特例を受けることができる土地についてもその要件、特例の適用面積や減額率といくつか選択ができます。
ここでは、小規模宅地の特例の制度を適用する際の具体的な内容について説明します。
《目次》
1.小規模宅地等の特例とは
2.特定居住用宅地等
3.特定事業用宅地等
4.貸付事業用宅地等
5.相続財産の分割が未分割の場合
6.まとめ
小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例は、相続する土地の評価額を最大80%まで減額して相続税を計算できる制度です。
土地の地価の高騰等をふまえて、相続税の負担で住まいの土地や事業で利用している土地を売却しなければならない事態を考慮し、相続人の生活基盤や事業基盤を継続する制度として設けられています。
小規模宅地等の特例によるメリットは、遺言や遺産分割協議で相続する土地にかかる相続税を大幅に減額することができる点です。
土地そのもの価値は変わらなくても、相続税を計算する土地の評価額が特例の計算で低減され、相続税額も低減分減額されます。
法定相続人でない人が、遺言で土地を取得した場合でも要件をみたせば特例の適用は受けられます。
小規模宅地等の特例の適用を受ける場合は、相続税の申告が必要となります。仮に、小規模宅地等の特例の適用を受けて計算した結果、相続税額が0円で税金を納める必要がない場合でも、申告書の提出は必要になります。
具体的に、小規模宅地等の特例の対象となる土地の種類は、下記の一覧のとおりです。
| 宅地等の種類 *1 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 | 330㎡まで | 80% |
| 特定事業用宅地等 | 400㎡まで | 80% |
| 貸付事業用宅地等 | 200㎡まで | 50% |
*1 「宅地等」の末尾の「等」は、宅地だけではなく、宅地の上にある借地権なども権利も対象に含まれます。
特定居住用宅地等
特定居住用宅地等とは、被相続人の自宅がある土地を配偶者や一定の条件の親族が相続したときに適用され、自宅の土地のうち330㎡までの部分の評価額を80%減額することができます。
例えば、相続税評価額1億円の土地で特定居住用宅地等に該当すると、80%の8,000万円が減額でき、2,000万円を財産額として相続税の計算を行います。
特定居住用宅地等の適用を受ける場合、次のうちいずれかに当てはまることが必要です。
| 相続する人 | 要 件 |
|---|---|
| 配偶者 | なし |
| 同居親族 | ・申告期限までその土地を持ち続けていること ・申告期限までその家屋に住み続けていること |
| 別居親族 | ・被相続人に配偶者や同居していた親族がいないこと ・申告期限までにその土地を持ち続けていること ・相続開始前3年以内に日本国内にある配偶者、3親等内の親族、特別の関係のある法人の所有する家屋に住んでいないこと ・相続開始前に住んでいた家屋を過去に所有したことがないこと |
特定事業用宅地等
特定事業用宅地等とは、被相続人が貸付事業用以外の個人事業や会社経営を営んでいて、事務所、店舗や工場などの建物に使用されていた土地に適用されます。その土地のうち400㎡までの部分の評価額を80%減額することができます。
被相続人が相続の開始前からその土地で事業を行っており、親族が相続税の申告期限(10ヶ月)までその事業を行っていることが要件となります。
特定事業用宅地等の適用を受ける場合は、次の要件を満たす必要があります。
| 相続する人 | 要 件 |
|---|---|
| 親族 | ・申告期限までその土地を持ち続けていること ・相続人が申告期限までに事業を受け継ぎ、引き続き事業を営んでいること |
事業を営んでいた土地を相続人が相続しても、相続人に事業の継続の意思がない場合や、申告期限までに事業を引き継いでいない場合は、この特例の適用は受けられません。
また、事業を引き継いだ後、申告期限までに事業をやめてしまった場合も、この特例の適用は受けられません。
賃貸アパートや貸駐車場など貸付事業に貸していた土地は「貸付事業用宅地等」に分類されます。
貸付事業用宅地等
貸付事業用宅地等とは、被相続人が貸していたアパートや賃貸マンション、駐車場地の土地に適用され、その土地のうち200㎡までの部分の評価額を50%減額することができます。
被相続人が相続の開始前からその土地を貸しており、親族が相続税の申告期限(10ヶ月)まで貸付けを行っていることが要件となります。
貸付事業用宅地等の適用を受ける場合は、次の要件を満たす必要があります。
| 相続する人 | 要 件 |
|---|---|
| 親族 | ・申告期限までその土地を持ち続けていること ・相続人が申告期限までに貸付け事業を受け継ぎ、引き続き貸付け事業を営んでいること ・相続の開始前3年以内に、貸付け事業を始めた土地等でないこと |
貸しているアパートやマンションの土地のうち、空室に相当する部分については、原則として小規模宅地等の特例は適用できません。
駐車場や駐輪場を貸している場合、その土地についても小規模宅地等の特例を適用することができます。
ただし、小規模宅地等の特定を適用する土地は、建物や構築物の敷地である必要があります。そのため、駐車場や駐輪場に建物や構築物があることが適用の要件とされます。
具体的には、立体駐車場、タワー駐車場、パレット式駐車場などは、建物や構築物の設備があるため、小規模宅地等の特例を適用することができます。
砂利敷きや芝生敷きの青空駐車場は、小規模宅地等の特例を適用できないケースがあります。コインパーキングの設備や舗装設備などの設置がされて、明らかに駐車場業を行っていることの判断が必要です。
相続財産の分割が未分割の場合
相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらなかった場合、未分割のまま相続税の申告を行います。
ただし、未分割の相続財産については、小規模宅地等の特例が受けられないため留意が必要です。
この場合、相続税の申告書を提出する際に、「申告期限後3年以内の分割見込書」の届出書を添付して申告します。
この届出書を提出されると、申告期限から3年以内に遺産分割協議がまとまれば、小規模宅地等の特例の適用を受けて相続税の計算をすることができます。
具体的な手続きは、遺産分割協議が決まってから4ヶ月以内に「更正の請求」という手続きにより、当初未分割で申告した相続税のうち納めすぎた税額分が還付されます。
まとめ
小規模宅地等の特例の具体的な内容について説明いたしました。
小規模宅地等の特例の適用を受けられると、土地の評価額の減額効果が大きく、相続税の負担もおさえられ、土地の評価額が大きいほど節税効果に反映されます。
相続税の申告手続では、小規模宅地等の特例を受ける場合、原則として当初申告で適用計算を記載し、添付資料と合わせて申告することが必要です。
また、小規模宅地等の特例を受けて相続税が生じない場合や、相続税の基礎控除内におさまる場合でも、申告が必要になりますので、申告手続きでの留意が必要です。
相続税の申告では相続税の負担を軽減する制度があります。こうした制度を適用して申告、税金の計算を行うことで相続税の節税効果にもつながります。
相続税の申告でお困りやお悩みがありましたら、ご相談ください。
関連するページのご紹介
こちらのページを読んだ方には、下記のサービスページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
お問い合せ・初回のご相談はこちら

税務・財務のご相談を受け付けております。
アクセス
住所
〒110-0005
東京都台東区上野3丁目16-2 413号
最寄り駅
・JR 御徒町駅より徒歩4分
・銀座線 上野広小路駅より徒歩4分
・大江戸線 上野御徒町駅より徒歩4分
・千代田線 湯島駅より徒歩4分
・京成線 京成上野駅より徒歩9分
・JR 上野駅より徒歩12分
営業時間
9:30~18:00
定休日
土曜日・日曜日・祝日