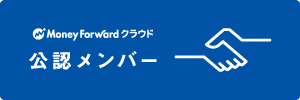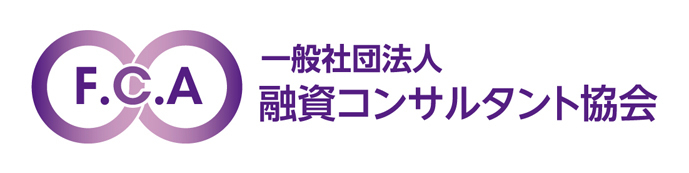お電話でのご依頼・お問い合せはこちら
相続税の申告の流れ

相続税の申告と納税は、相続が発生した日の翌日から10ヶ月以内に税務署へ申告書の提出と納税が必要になります。
この期限を過ぎてしまうと延滞税などの追徴課税のペナルティが発生し、相続税の税額が軽減できる税制の特例のメリットが受けれなくなります。
相続税は被相続人がお亡くなりになられてからやるべきことや各種手続きも多くあり、10ヶ月の申告期限もあっという間に過ぎてしまったというお話も伺います。
ここでは、相続後の相続税の申告の流れ、相続人が具体的に対応すべきことについて説明します。
《目次》
1.相続発生から相続関係手続き・相続税申告までの流れ
2.相続人の確認
3.準確定申告
4.相続財産の調査と確認
5.遺産分割協議書の作成
6.相続税の申告書の作成と納税
7.遺産分割協議が成立していない場合
8.相続税の申告と納税が期限までに間に合わない場合
9.まとめ
相続発生から相続関係手続き・相続税申告までの流れ
相続に関する手続きは数多くあり、期限が設けられている手続きもあります。
相続が発生してから一般的な相続関係の手続きや相続税の申告までの相続後の経過月に合わせた流れは、下記の通りです。
| 相続後の経過月 | 手続関係 | 期限 | 手続先 |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月~2ヶ月 | 年金受給権者死亡届 | 14日以内 | 社会保険事務所等 |
| 未支給年金・保険給付請求手続き | 相続後 | 社会保険事務所等 | |
| 遺族年金・死亡一時金請求手続き | 相続後 | 社会保険事務所・市区町村 | |
| 死亡保険金支払請求手続き | 相続後 | 生命保険会社 | |
| 役員の変更(会社の役員に就任されていた場合) | 可決後2週間以内 | 法務局 | |
| 遺言の確認 | 相続後 | 家庭裁判所等 | |
| 相続人の確認 | 相続後 | ||
| 3ヶ月 | 相続放棄手続き | 3ヶ月以内 | 家庭裁判所 |
| 限定承認手続き | |||
| 4ヶ月 | 被相続人の準確定申告 | 4ヶ月以内 | 税務署 |
| 個人事業の承継 | 税務署等 | ||
| 個人事業承継者の青色申告承認等の届け出 | 税務署 | ||
| 10ヶ月 | 遺産分割の協議、遺産分割協議書の作成 | ||
| 相続税の申告と納税 | 10ヶ月以内 | 税務署 | |
| 相続税の延納手続き | |||
| 相続税の物納手続き | |||
| 12ヶ月 | 遺留分の減殺請求 | 12ヶ月以内 | 家庭裁判所 |
| 遺産分割後のその他の手続関係 | 手続先 |
|---|---|
| 不動産の名義変更 | 法務局 |
| 銀行預金の名義変更 | 銀行 |
| 上場株式等の株式名簿の名義変更 | 信託銀行等 |
| 非上場株式等の株式名簿の名義変更 | 発行会社 |
| ローン承継、保証債務等の承継 | 銀行等 |
| 電話加入権の承継、改称届 | 電話局 |
相続税の申告と納税は、相続後10ヶ月以内に行う必要があります。相続後は相続財産の確認、財産目録の作成、遺産分割協議の決定など期間内に手続きを進めて行くことが重要になります。
相続人の確定
相続の手続きにおいて遺言書がある場合には、遺言書にそって遺産を分けます。遺言書がない場合には、法定相続人全員で話し合いによって遺産の分け方を決めて行くことになります。
その際、法定相続人が誰なのかを確認する必要があり、被相続人と相続人の戸籍謄本をそれぞれの本籍地の市役所や町村役場で取得をして相続人を確定していきます。
準確定申告
「準確定申告」とは、お亡くなりになられた被相続人の所得税の確定申告のことをいい、その年の1月1日からお亡くなりになる日までの所得税について相続人が申告します。
準確定申告をする場合に提出する申告書は、一般の確定申告に準じた確定申告書として「準確定申告書」といいます。
準確定申告の申告期限は、相続発生の日の翌日から4ヶ月以内に申告を行わなければなりません。所得税の納税につきましても、申告期限と同じになります。
この準確定申告の手続きは、相続人が申告と納税を行います。
なお、準確定申告を申告することで税金の還付を受ける場合には、4ヶ月以内の期限はありません。税金還付請求できる5年以内に申告することで、還付を受けることができます。
相続財産の調査と確認
相続税の申告や遺産分割協議において、被相続人の相続財産の対象となる財産、債務を確定していきます。
財産は、不動産や預貯金、有価証券、ゴルフ会員権、書画骨董品など、債務は借入金、住宅ローン、葬祭費などが対象になります。
その他にも生命保険金や退職金がある場合、みなし相続財産として相続税の課税の対象となります。
相続税を計算するときの財産の評価金額は、相続時の時価になります。時価の評価金額の計算は、相続税の財産評価のルールにそって計算します。
なお、相続できる遺産は、財産から債務の金額を差し引いたものになります。債務が財産より多い場合は、預貯金などの財産で支払うことになるため、支払って何も残らなかったり債務しか残らなかったということもあります。
そのため、財産、債務についてはすべて調べて、何が残るか金額を計算して早めに確認していくことも重要です。
遺産分割協議書の作成
遺言書がのこされていない場合は、相続人全員で相続財産の遺産分割協議を行い、財産の受け継ぎを決めていくことになります。分割協議がまとまれば遺産分割協議書を作成することになります。
遺産分割協議書は、相続税の申告書への添付資料として必要になるほかにも、不動産を遺産分割によって所有権を移転するときに所有権移転登記の申請のときや、銀行預金を遺産分割協議で相続人のうちだれかが受け継いで解約や名義変更するときにも必要となります。
遺産分割協議書には、相続人全員が各自署名し、実印を押印することとされています。その際、「印鑑証明書」の添付も必要になります。
相続税の申告書の作成と納税
相続税の申告と納税は、相続発生の日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。
申告書の提出は、お亡くなりになられた方の住所を管轄する税務署に提出する必要があります。納税は現預金での一括納付が原則ですが、分割払いによる延納の特例や不動産などでの物納の特例もありますが、いずれも10ヶ月以内に申告が必要です。
ただし、遺産の総額が相続税の基礎控除額以下の場合には、相続税はかからず、相続税の申告をする必要はありません。
相続税の基礎控除とは、相続税の計算をする際に遺産総額から差し引くことができる金額をいい、下記の算式で計算されます。
【基礎控除額の計算式】 基礎控除額 = 3,000万円 + (法定相続人の数 × 600万円)
法定相続人の数の相続税の基礎控除額を下記にまとめています。
| 法定相続人の数 | 相続税の基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
| 6人 | 6,600万円 |
相続税が発生しない場合でも、相続税の計算で小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など適用する場合には、相続税の申告の提出が必要になります。
遺産分割協議が成立していない場合
10ヶ月の相続税の申告期限までに遺産の分割ができなかったときは、法定相続分で相続財産を引き継いだものとして相続税を計算して申告することになります。
なおこの場合には、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの適用を受けることができないため、相続税の申告に注意が必要です。
その際に、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出することで、相続税の申告期限から3年以内に遺産を分割し、相続税の計算の特例の適用を受けるための手続きがおこなえます。
さらに、相続税の申告期限の翌日から3年後に、相続等に関しての訴えが提起されているなどやむを得ない事情で遺産の分割がまとまらない場合に、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出することで、判決後に遺産の分割が決定した時点で、相続税の計算の特例の適用を受けることができます。
相続税の申告と納税が期限までに間に合わない場合
相続税の申告期限までに必要な相続税の手続きが間に合わず、申告手続きが遅れた場合や相続税の納税が遅れてしまう場合は、罰則としてペナルティがかかってきます。
罰則としてのペナルティは、申告を行わなかったことによる無申告加算税と納税が遅れたことよる延滞税になります。
| 無申告加算税 | 無申告加算税は申告が必要な場合、申告期限までに申告をしなかったことに対してかかります。 ペナルティ的な性格で、申告によって支払うべき相続税に対して加算されます。 税率は、申告期限を過ぎて税務調査を受ける前に自主的に申告した場合と、税務調査を受けてから申告した場合とで率が異なります。 |
|---|---|
| 延滞税 | 延滞税は申告期限までに、納付しなかった相続税に対してかかります。利子的な性格になります。 税率は期間に応じて、税額は本来の納付期限の翌日から相続税を納付した日までの日数に応じて計算されます。
|
〇無申告加算税の税率
| 相続税の税額のうち | 税務調査の事前通知より前に自主的に申告した場合 | 税務調査の事前通知を受けてから税務調査を受けるまでに申告した場合 | 税務調査を受けてから申告した場合* |
|---|---|---|---|
| 50万円以下の部分 | 5% | 10% | 15% |
| 50万円超の部分 | 15% | 20% |
*過去5年以内に相続税で無申告加算税または重加算税が課されたことがあるときは、税率が10%加算されて、50万円以下の部分は25%、50万円超の部分は30%になります。
〇延滞税の税率
| 期 間 | 納期限の翌日から2月を経過するまで | 納期限の翌日から2月を経過した日以後 |
|---|---|---|
| 2021年1月1日から2021年12月31日 | 年2.5% | 年8.8% |
| 2020年1月1日から2020年12月31日 | 年2.6% | 年8.9% |
| 2019年1月1日から2019年12月31日 | 年2.6% | 年8.9% |
| 2018年1月1日から2018年12月31日 | 年2.6% | 年8.9% |
| 2017年1月1日から2017年12月31日 | 年2.7% | 年9.0% |
| 2016年1月1日から2016年12月31日 | 年2.8% | 年9.1% |
| 2015年1月1日から2015年12月31日 | 年2.8% | 年9.1% |
延滞税は相続税の本税部分のみを対象としてかかり、無申告加算税にかかりません。
まとめ
相続は複雑な手続きが多く、相続税の申告は申告期限も設けられているため、スケジュールを確認しながら進めていくことが重要になります。
相続税の計算には基礎控除があり、この基礎控除額より相続する財産の総額が下回る場合は、相続税はかからず申告も必要ありません。
相続財産の総額によって相続税が決定されるため、まずは財産を確定したうえで、財産の総額が基礎控除を超えているかどうかが申告の判断のポイントになります。
また、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など相続税の優遇措置が設けられており、基礎控除額より相続した財産が上回っている場合でも、優遇措置を適用することで相続税が発生しない場合もあります。その際には、相続税の申告は必要になります。
相続税の申告では相続税の負担を軽減する制度があります。こうした制度を適用して申告、税金の計算を行うことで相続税の節税効果にもつながります。
相続の手続きや相続税の申告について、お悩みやお困りごとに直面している場合は、お問合せ・ご相談ください。
関連するページのご紹介
こちらのページを読んだ方には、下記のサービスページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
お問い合せ・初回のご相談はこちら

税務・財務のご相談を受け付けております。
アクセス
住所
〒110-0005
東京都台東区上野3丁目16-2 413号
最寄り駅
・JR 御徒町駅より徒歩4分
・銀座線 上野広小路駅より徒歩4分
・大江戸線 上野御徒町駅より徒歩4分
・千代田線 湯島駅より徒歩4分
・京成線 京成上野駅より徒歩9分
・JR 上野駅より徒歩12分
営業時間
9:30~18:00
定休日
土曜日・日曜日・祝日