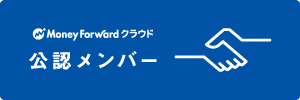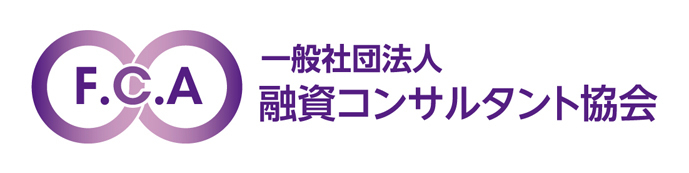お電話でのご依頼・お問い合せはこちら
金融機関が考える借入限度額

会社経営を行っていく上で、重要になるのが「資金繰り」「融資」です。必要な資金を調達できるかできないかで、事業経営の運営方法も変わってきます。
そのためにも、「あとどれくらい借りられるのか?」ということは資金繰りと合わせて気になる点になります。
ここでは、金融機関が考える借入限度額の目安とその計算方法について説明いたします。
《目次》
1.償還年数から借入限度額の計算
2.月商や年商(月商倍率)から借入限度額の計算
3.経常利益から借入限度額の計算
4.まとめ
償還年数から借入限度額の計算
償還年数とは、債務をすべて返済するために必要な年数で、債務を年間返済可能額(税引き後利益+減価償却費)で割ることで計算ができます。
一般的に、借入金が多いほど償還年数は長くなり、借入金が少ないほど償還年数は短くなります。
計算式 : (税引き後利益 + 減価償却費) × 10
担保や保証人の有無、取引年数、取引先との関係性を考慮しない場合、金融機関が貸し出し可能金額の目安とされるのが「年間返済額の10年分」です。
通常、償還年数の適正な水準は5年以内ですが、一般的に融資限度額を計算する場合は、償還年数を10年として考えます。
償還年数から計算する計算式の分母は「税引き後利益+減価償却費」であるキャッシュフローです。「税引き後利益」と「減価償却費」の金額が大きく計上されると、償還年数により借入限度額にも有利になります。
そのため、償還年数からの借入限度額の計算の上、「利益の最大化」と「減価償却費の適正化」により改善を図ることができます。
月商や年商(月商倍率)から借入限度額の計算
金融機関で簡易的に「借入限度額の目安」を判断するときに、よく使われる計算です。
月ごとの売上である月商の何ヶ月分の借入が限度額にあたるか指標から算出されます。
決算書や損益計算書の数値から平均的な月商で計算ができ、今の借入金残高から借入限度額の目安を簡易的に判断する指標といえます。
計算式 : 月商(年商 ÷ 12) × 1~6ヶ月
借入限度額を月商倍率で計算する場合は、業種業態によって範囲が広がるため、概ね月商の1~6ヶ月を目安とされています。
営業利益率や経常利益率の高い業種の場合は、長い期間(5ヶ月~6ヶ月)で計算され、営業利益率や経常利益率の低い業種の場合は、短い期間(1~2ヶ月)で計算されます。
月商倍率による借入限度額の計算は、売上のみの数値で計算されるため、利益率や投資額などの数値が反映されないため重要視されない場合もあります。
実際の融資においては、粗利益額や利益率、安全性が高い収益ベース、返済能力の確実性の要素も加味して総合的に判断されると考えられます。
経常利益から借入限度額の計算
融資に際にて、厳格な基準で対応する金融機関の場合、経常利益から計算する方法により融資限度額の目安を計算します。
計算式 : 過去3年分の経常利益の平均 × 50% × 7
「経常利益の50%」は、税金の支払いを考慮した金額で「税引き後利益」に近い数字になります。
償還年数から借入限度額の計算や月商から借入限度額の計算と比べて、一般的に限度額は少なめの数字になります。
経常利益が右肩あがりで拡大傾向の場合、計算式の倍率の係数は7倍より増えていき、右肩下がりの縮小傾向の場合、計算式の倍率の係数は7倍より減少します。
会社の経常利益や経営状況により、倍数は5~10の係数の範囲で変動します。
月商や年商に関係なく、会社の収益性から借入限度額を計算するため、返済能力の安全性が担保された借入限度額が把握されます。
まとめ
融資の際の審査基準は、収益性、成長性、安全性、財務の健全性など総合的に判断され、金融機関が考える借入限度額を把握しておくことで、財務の信用度をあげることができます。
借入限度額を把握することで、借入過多になるリスクをおさえて、また借入返済に資金繰りが厳しくならない予防判断につながります。
借入限度額を超過している場合は、資金繰りを確認しながら、なるべく追加の銀行融資を行わずに、財務体質の健全化を図ることが大切です。
スムーズな融資を受けるためには、金融機関から信頼される決算書や月々の試算表を作成することが欠かせません。そのためにも、専門家のアドバイスを受けながら適切な準備を進めることをおすすめします。
事業資金や資金繰りに関するご相談に、融資・資金調達支援コンサルティング、キャッシュフローコーチ・コンサルティングの各サービスをご用意しております。
関連するページのご紹介
こちらのページを読んだ方には、下記のサービスページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
お問い合せ・初回のご相談はこちら

税務・財務のご相談を受け付けております。
アクセス
住所
〒110-0005
東京都台東区上野3丁目16-2 413号
最寄り駅
・JR 御徒町駅より徒歩4分
・銀座線 上野広小路駅より徒歩4分
・大江戸線 上野御徒町駅より徒歩4分
・千代田線 湯島駅より徒歩4分
・京成線 京成上野駅より徒歩9分
・JR 上野駅より徒歩12分
営業時間
9:30~18:00
定休日
土曜日・日曜日・祝日